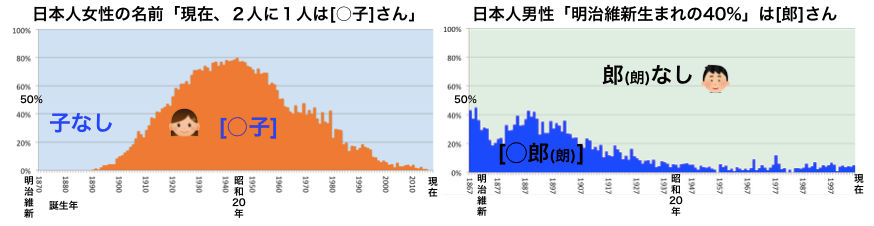(8)『女学雑誌』が女学生に[子]をつける
8-1 『女学雑誌』は[子]のオンパレード(明治18(1885)年--)
右は、日本初の女性週刊誌(月に2回発行)『女学雑誌』の明治18(1885)年創刊号(7月20日)表紙です。その右は、創刊号2ページに掲載された「宮内省女官録」で、[子]のつく名前が並んでいます。さらに下は、第3号(8月25日)には、「女子師範学校」の卒業生名がすべて[子]つきで並んでいます。同じく3号には和歌が掲載され、4人中3人が[子]つきです。
まさにこの雑誌は、「[子]のオンパレード」です。『女学雑誌』とはどういう雑誌なのでしょう。創刊号の「発行の趣旨」には次のように書かれています。
西洋学者の言に、国内婦人の地位いかがをみればもって、その国文明の高下をさとるべしと言えり。わが国現今の婦人を見て、「日本はなお開化せし国に非ず」と言われん......われらの母、われらの姉、われらの妻のなにゆえに、かく世に軽ろしめらるべきものなるやを憂い、さきに女学雑誌を発刊して、専ら婦女改良の事に勉め(以下、略)

『女学雑誌』が創刊された明治18(1885)年は、ちょうど「鹿鳴館」での舞踏華やかな時代(1883-1887)でした。前年に「華族令」が出され『華族名鑑』に[子]のつく女性名が並んだ時代です。条約改正に向け「西洋をまねて女性の存在を表に出そう」という社会の動きがあったのです。また明治7(1874)年の「東京女子師範学校」をはじめ、いくつかの女学校ができ、女学生の時代が始まった時期でもあります。
そんな『女学雑誌』の読者には、『自分の名前に[子]をつけていいのか」と疑問を投げかける人もいました。
第2号(1885年8月10日発行)の質問コーナーには次のような「問」が寄せられています。
「●子の字の問(七 婦人の名に何々子を称する子の字は、いかなる義理なるか(静岡 近藤しげ)」
この「問」に対して、編集部は第5号(1885年9月25日)で次のように答えます。
「●子の字の答(七)婦人の名に何々子と子の字を付するは、これ婦人の美称にして、姫というがごとし。また男児に郎というも同じもとと、姫も子も漢土の姓氏にして、のち遂に美称となる。我が国にても姫氏国と称えし程にて、古来より姫と称せり、子と称するは、漢字の盛んなりし頃より多く称するに至る。もっとも、姫は高貴な人に用い、子は中等に用いしが如し。然れども今は区別なきが如し(若宮微古迂史) 」
つまり「[子]は敬称である」ということです。今まで述べたように、明治維新以前は、[◯子]は宮中の女性のみに許された名前でした。そんな「子]は、華族の女性に、自由民権の女性たちに広がっている状況です。それを『女学雑誌』は肯定的に書いているのです。さらに『女学雑誌』はもう一人の弁を掲載しています。
「●同上の答 按ずるに、鶏肋編(*)に「燕山の娼妓みな子を以って名をなす。香子、花子の類のごとし」とあり、本邦女子の名に子の字を用いて花子、貞子などと称するも、これらにもとづきしなるべし。別に意義はあるまじ(西島楳所)」(*「鶏肋編」宋時代, 荘綽が雑事記聞を集めた小説筆記の類)
この筆者は、中国の古典を引いて、述べています。同年1月29日の新聞記事「華族婦人のとなえ」は「(華族婦人は)[子]の字を付すべし」と報じます。それは同時に「身分の低い者は[子]をつけるな」という意味でもあります。西島という筆者は、[子]がついていても「別に意義はない」と書いているのです。

ただ『女学雑誌』は、すべての女性名に[子]をつけたわけではありません。「女学校の卒業生一覧」を見ると、[子]をつけたり、つけなかったりして号を進めています。
時代は、行きつ戻りつ、[子]の流行に向かっていくのです。
『女学雑誌』には、[子]のつく名前の有名人が登場しています。
若松賤子 138回 (本名かし、「小公子」翻訳、掲載)
岸田(中島)俊子 47回 (本名とし)
荻野吟子 5回 (本名ぎん、日本最初の女医)
津田梅子 7回 (本名むめ)
下田歌子 4回 (本名せき)
*回数は、青山・野辺地・松原著『女学雑誌諸索引』(慶応通信1970)より数える
8-2 二葉亭四迷『浮雲』の主人公は「お勢?」「勢子?」(明治20(1887)年)
その当時の社会状況を知るのに、うってつけの小説があります。『浮雲』(1887-89)です。主人公は「お勢」数え年で15才でしょうか。小学校を卒業して私塾に2年間通います。英語を学びはじめ、装いも変わっていきます。それも塾をやめてしまいます。主人公の文三(18才くらい)は、お勢から英語を習っています。ある日、文三といっしょにいた弟の勇のシャツを、洗濯するために脱がせて持っていってしまいます。弟はグチをこぼします。
「オイオイ姉さん、シャツを持ッてッとくれッてば……オイ……ヤ失敬な、モウいっちまッた。あいつ近ごろ生意気になっていかん。さっきも僕アけんかしてやったんだ。婦人(おんな)のくせに園田勢子と云う名刺(なふだ)をこしらえるッてッたから、お勢ッ子で沢山だッてッたら、非常に憤(おこ)ッたッけ。」「お勢ッ子で沢山だ、婦人(おんな)のくせにいかん、生意気で。」岩波文庫1941初版,1995第65刷,p.114より
「お勢さん」は、女学校に通うようになって自分のことを「勢子と呼んで」とばかりに「名刺(めいし)」を作ったのです。ただこのページを、最初の最後として「勢子」という名前は出てきません。
いずれにしても『浮雲』の「勢子」は小説の登場人物として「最初の[◯子]さん」と言っていいでしょう。
この一節の発見は、私にとって衝撃的でした。ちょっと横道にそれますが、紹介します。
私は「小説の登場人物の中に[◯子]がいつから現れるか」が気になっていました。そこで『近代文学作中人物事典 月刊國文學 1991.9月臨時増刊号』(學燈社)を見ていました。そこに「勢子」があったのです。ふつう「『浮雲』の主人公は[お勢]」ということになっています。しかしその本は「勢子」だったのです。
岩波文庫『浮雲』を買ってきて、ページをいくらめくっても「お勢」ばかりです。あきらめてその本を横に置いておいたら、隣に座っていた友人の橋本さんが、「ここにあるよ」とp114を見つけてくれたのです。やはり「持つべきものは研究友だち」です。
続きは↓
(9) ラフカディオ・ハーン「[子]は〈Lady〉」と言う。
➡️ 「女性名と[子]の目次」に戻る
| セル1 | |||||
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から